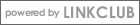December 23, 2008
フランス革命は「図書館革命」にならず
フランス革命と言っても、1789年に始まり、ナポレオンの登場により集結するのを、フランス人たちは大革命と呼んでいる。ナポレオンがセントヘレナ島に流されたあと、王政復古になり、1830年に7月革命が起きても王政が続き、1848年の2月革命で共和政になり、またナポレオン3世の第2帝政が始まり、と二転三転しながら、共和政が確立してゆく。ところで、フランス革命は図書館の発展に大きな影響があったかというと、無かったと言うべきであろう。むしろ、悪影響だったというのが正解。大革命によって、王政が廃止されると、まず王立図書館、つまり国王所蔵の図書館は政府に没収されて、民衆に開かれた国立図書館になる。貴族や修道院が所蔵していた書物も、すべて政府に没収されて、各地の図書館になった。と書けば、一部の王侯と貴族、修道僧たちが知識を独占していたのが、民衆のものとなって、良かったじゃないかと思われるかもしれないが、この当時、民衆が通う学校がなく、識字率はきわめて低く、革命の活動家を除くと、図書館の恩恵を受けた民衆は少ない。
おそらく、革命のどさくさで、散逸した書物が多かったに違いない。なにしろ、貴族の館だ、修道院だと、民衆があたりかまわず襲撃していたのだから、書物を大切にしようなんて気は起きなかっただろう。知識のある貴族や聖職者は、亡命するか、ギロチンの犠牲になるかのどちらかだったし。
フランスで、今のように街のあちこちに図書館がつくられて、広く利用されるようになるのは、意外と最近のことで1980年代からなのだ。
もともと公立図書館は、19世紀後半からイギリスとアメリカで発達した。イギリスも、アメリカも、ヨーロッパ大陸からは隔たった地で、ギリシア・ローマ、そして中世、ルネサンス以来の学問の伝統が無いために、人々が大陸からもたらされる知識を共有したいという欲求から始まったのが公立図書館である。またイギリスも、アメリカも、プロテスタントの国だから、飲酒の習慣をやめさせて、労働力を高めるために、徒弟学校などで読書を勧めたのも要因である。
フランスをはじめとした大陸側の国々は、ギリシア・ローマの時代から引き継いだ学問と知識の伝統があったので、イギリスやアメリカのように、知識をみんなで共有しようという発想がなかった。知りたければ、そこにあり、そのうえ、身分制度のもとでは、生まれで職業が決まるから、無理して専門的な知識を学ぶ必要はなかった。
フランスで図書館に影響を与えたと言えば、むしろ、革命前にできた『百科全書』のほうが重要だろう。最も古い百科事典は他にあるが、分量として申し分のない、最新の知識と技術を盛り込んだ百科事典は『百科全書』と言える。まさに啓蒙主義の集大成と言える。
13:29:59 |
falcon |
comments(0) |
TrackBacks
「フランス革命」にハマる
Falconは大学入試の社会科で世界史を選択して、かなり勉強した。覚えることがたくさんあったので、最近はかなり忘れかけている。フランス革命といえば、池田理代子さんのコミック『ベルサイユのばら』が思い出される。オスカルやアンドレは創作された人物だけれども、オスカルのように男装の麗人はフランス革命で大活躍していたらしい。
というのも、安達正勝著『物語フランス革命』(中公新書)で、民衆の側で男装して、他の男の兵士とともに、戦った女性たちがいたという記述を読んで、驚いた。もっとも、オスカルのような国王側の近衛兵にはいなかっただろうけど、フランス革命で活躍した男装の麗人は全くの嘘ではないらしい。
ルイ16世と言えば、王妃マリー・アントワネットの言いなりで、錠前づくりと狩猟が趣味、政治力の欠如した、鈍重、凡庸な王様という印象が強い。しかも、肖像画を見ても、垂れ目で、でっぷりとした肥満体形、人の良さそうな、お育ちの良いオッサンにしか見えない。お爺様のルイ15世は、少なくともブルボン家の国王の中ではとびきりの美男、おそらくフランス史上でも最もハンサムな国王だろう。ルイ15世の曾お爺様のルイ14世は太陽王と言われただけに、豪壮華麗な衣装に身を包み、威厳をたたえた表情は王の鑑ともいえる。それに引き替え、ルイ16世の何とも言えない頼りなさと言いたいところだが、本書を読むと、意外にも英邁で、革命に共感して、推進した優れた国王であることがわかる。バカ殿のイメージは、革命後につくられたものなのだろう。
同じく安達氏が以前に出版した『死刑執行人サンソン:ルイ16世の首を刎ねた男』(集英社新書)も続けて読んだ。フランス革命の影の主人公である死刑執行人の波乱に満ちたドラマで、フランス革命のもう一つの歴史が語られる。革命期だけで2,000人以上の人が断頭台で命を落とした。すべての最期の姿を見届けたのが、シャルル・アンリ・サンソンだ。言われもない差別を受けて、苦悩の果てに、国王をも手にかけた男の胸の内を知り、革命という名のもとに、多くの人々の血が無残に流されたことを直視すべきと思う。
ちょうど読んでいる最中に、映画『ブーリン家の姉妹』を見た。こちらは、フランス革命よりも300年くらい前の話だ。
エリザベス1世の母であるアン・ブーリンとその一族の物語。当然、シェークスピアなどの歴史劇を下敷きにしているのだけれども、台詞回しが恐ろしいくらいに胸にしみる。
男子を産むことのできなかったアン・ブーリンは、処刑されるのだけれども、高貴な人の待遇で、斬首される。当時は、庶民は絞首刑で、身分の高い人は斬首だったらしい。これはフランス革命の直前まで変わらなかった。革命中に、身分の低い人も、貴族と同様にギロチンの犠牲になった。
アン・ブーリンの罪状は、反逆罪並びに近親相姦罪。エリザベスの出産後、王の子を宿せなかったために、多くの男と交わり、兄弟とも交わったという。そういえば、王妃マリー・アントワネットも、実の子と交わったという罪とともに、断頭台にかけられた。たとえ罪を問うにしても、近親相姦という屈辱的な罪を着せて問うのは、余りにも残酷すぎる。
この後は佐藤賢一さんの『小説フランス革命』を読もうと思っている。そういえば、塩野七生さんの『ローマ人の物語』の続きが出版された。正月は読書三昧になりそうだ。
12:20:03 |
falcon |
comments(0) |
TrackBacks